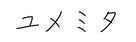私はどこかの大学へ通う学生のようで、講義を受け終わった後に担当の教授から「部屋にこのプリントを運んでおいてくれ。」と頼まれました。
どうやらその大学内で私は真面目な学生で優等生として頼りにされているようです。「わかりました!任せてください。」と笑顔で返事をして、プリントを教授の部屋まで運びます。
教授の部屋に入り、机の上にプリントを置いてふと横を見ると実験器具のような物が置いてあることに気が付きました。
液体が2種類、別々の瓶の中に入れられています。それらは透明な液体で、瓶の蓋には穴があけられて管が通されています。2つの液体がその管を通り撹拌機の上に置かれたビーカーの中へと注がれるようにして置かれています。今は液が混ざり合わないように管にストップコックが取り付けられています。
なぜかそれらが気になって仕方がありません。「やってはいけない事」と分かりながらも、管に取り付けられたコックへと手が伸びました。
私はコックを開けて2つの液体が管を通ってビーカーの中へと流れる様子をじっと眺めました。ビーカーの3分の1ほど液体が入ると、急にビーカーの中で混ざった液体が沸騰したかのように泡を立てながらグツグツと言い始めます。この時初めて「とんでもない事をしてしまったのかもしれない!」と酷く焦り、急いで管のコックを閉めました。
ビーカーへと流れる液は無事止まりましたが、ビーカーの中で混ざり合った液体の沸騰は続きます。しかも段々と量が増えていきます。3分の1ほどしかなかった液体が溢れそうになっているのです。「どうしよう!これ以上増えると教授の机が大変な事になる!止まって!」と焦りながら私は咄嗟に自分の手でビーカーに蓋をします。
すると液体はそれ以上増えなくなりました。が、手を火傷してしまいました。
火傷の痛みより「大変なことをしてしまった。」と心が痛くてパニックになります。どうしよう、どうしよう…。私は2種類の液体が混ざったビーカーを手に持ち、その場を去りました。平静を装いながら廊下を歩きますが、内心は焦りとパニックで心臓バクバク。すると、だんだんと悪い考えが浮かんできます。
混ぜる前の液体も、混ぜた後の液体も「透明」だったし…。このまま混ぜ合わせる前の液体が入った瓶の中に戻せばバレないかもしれない!と。それは強迫観念にも似た感覚で、私は急いで教授の部屋へと戻ります。そして、それぞれの瓶の蓋を開けて混ざり合った液体が半分ずつになる様に液を戻していきました。見た目では全く分からない状態でした。
私はソワソワしながらも、一度家へ帰ることにしました。ずるい事に「もしかしたらバレないかもしれない…。」と思っていましたが、同時に「絶対にこの事を伝えた方がいい。」とも思っており、まるで天使と悪魔が語り掛けてくるようでした。家に着き、自室へ向かい鞄を下ろしてベッドに寝ころびます。常に頭の中には「どうしよう。」と言う焦りが浮かんでいました。落ち着く事もできず、私はリビングへと向かいます。
すると、台所で料理を作っていた母が私の方へ近づき新聞を渡してきました。「ねえ!ここに載っている教授って、大学の〇〇先生よね?」と、指をさします。
見出しは確か「新薬発見!」だったと思います。そこには教授の写真と、聞いたことも無いような液体の名前が2つ書かれていて、上下には子供たちの写真が載っています。母親が畳みかけて「凄いわよね!この薬で子供たちが救われるのよ~!貴方も、こんな素晴らしい教授さんと一緒の大学で学べるなんて素敵な事よね~。」とニコニコしています。
私は新聞を手に持ち、(あの液体ってもしかして!!)と血の気が引きました。私があのコックを触ってしまったが故に救えない命が出たらどうしよう等色々と考え、隠蔽しようとした自分を恥じ、嫌悪しました。そして私を信じてくれている教授や母の事を思うと、なんて馬鹿な事をしてしまったのだと震えました。
極めつけに、液体の分量は少しの誤差があってはならないと書かれているのです。「14」と言う数字が度々出てきて、凄く大事なようです。新聞には教授が手で書いた数式や、混ぜ合わせる前の液体すらも緻密な計算の上で出来あがった物だと知り、私はさらにパニックに陥りました。私が液体を元の瓶に「適当に目分量で」半分ずつ戻して隠蔽しようとしたせいで、何もしなければ無事だった瓶の中の液体自体すらもダメにしてしまった可能性が高かったからです。
私は、泣きそうになりながら教授へ電話をかけようとします。
許されなくてもいい、怒鳴られたって、大学を辞める事になってもいい…。もしかしたら訴えられるかもしれない。逮捕されるかも….しかし、自分がやってしまった事を全て伝えなければ!!!震える指で教授の電話番号を入力し、時計をふと見る23時。電話をかけるには非常識な時間かも知れない。でも明日じゃなく今すぐに伝えて謝らないと…。体に力が入り、全身がガタガタと震えます。
プルルル…。と、電話の呼び出し音が何度か鳴った所で私は目を覚ましました。ハァハァと息を切らしながら目を開けて息を整えると、夢だった事に気が付きホッとしました。